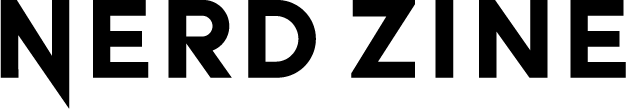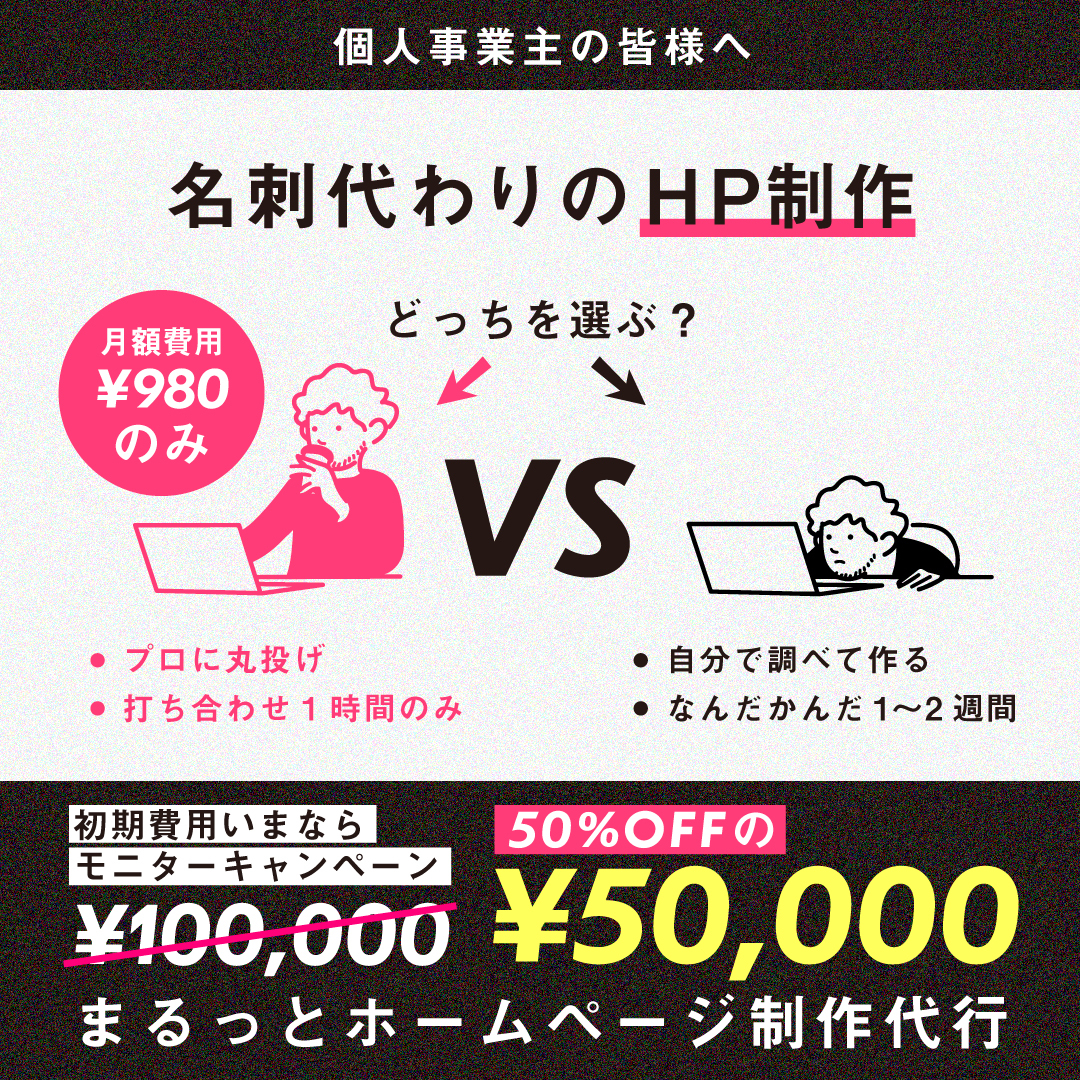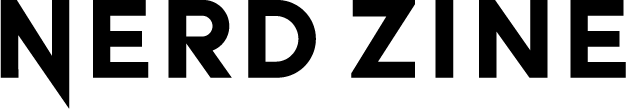「ホワイトペーパーがマーケティングに有効」と聞いたけれど、実際にどう活用すれば成果につながるのか分からない…
そんな悩みを抱えていませんか?
BtoB企業を中心に、見込み顧客(リード)獲得やナーチャリングの起点として注目されているホワイトペーパーですが、正しく企画・制作・活用しなければ、単なる“資料”で終わってしまうことも少なくありません。
本記事では、これからホワイトペーパー制作を検討する企業担当者に向けて、
- ホワイトペーパーの基本と役割
- 制作による具体的なメリット
- 種類や構成例、成功パターン
- 制作の流れと外注先の選び方
- 活用事例と成果につなげる実践テクニック
といった実践的な内容を、図解・事例・費用感まで含めて網羅的に解説します。
限られた予算やリソースの中でも、確実に成果を出すホワイトペーパーを作りたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むことで、すぐに制作に取りかかれるレベルの知識と視点が手に入ります。
目次
ホワイトペーパーとは?ビジネスシーンでの役割

ホワイトペーパーとは、特定のテーマや課題に対する専門的な情報をわかりやすくまとめた資料のことです。もともとは政府や公的機関が政策説明のために発行していた文書が起源ですが、現在では企業のBtoBマーケティングにおいて有力な営業支援ツールとして活用されています。
特に、自社の商品やサービスが抱える「顧客の課題をどう解決できるか」を示す手段として有効であり、顧客の信頼を得るための説得材料としての役割を果たします。
企業がホワイトペーパーを制作・活用する主な目的には、以下のようなものがあります。
- 見込み顧客(リード)の獲得
- 顧客の育成(ナーチャリング)
- 営業活動の効率化
- 自社の専門性や信頼性の訴求
また、最近ではマーケティングオートメーション(MA)ツールと連携し、ユーザーの行動データに基づいたコンテンツ配信の起点としても使われています。
なぜ今、ホワイトペーパーが注目されているのか?
Web広告やSNSの情報過多によって、ユーザーの目は年々厳しくなっています。そんな中でホワイトペーパーは、信頼性・専門性・実用性を兼ね備えたコンテンツとして、真剣に情報を探しているユーザーにとって価値ある資料として評価されているのです。
さらに、資料をダウンロードするという行動は購買意欲の高いサインでもあり、ホワイトペーパーを活用することで、より確度の高い見込み顧客を抽出できる点も大きな魅力です。
ホワイトペーパーは単なる「PDF資料」ではなく、営業とマーケティングの橋渡しを担う戦略的コンテンツ。そのビジネスシーンにおける役割は、今後ますます重要になっていくでしょう。
ホワイトペーパー制作のメリット

ホワイトペーパーは、単なる「資料」ではありません。戦略的なマーケティングコンテンツとして、企業にとってさまざまなメリットをもたらします。ここでは、特に効果が大きい3つのポイントに絞って解説します。
見込み顧客(リード)の獲得向上
ホワイトペーパーは、ターゲットとなる見込み顧客の興味・関心に合わせた情報を提供することで、リード獲得に大きく貢献します。例えば、業界課題に対する解決策や成功事例を紹介することで、ユーザーは「自社でも同じことができるかもしれない」と感じ、資料をダウンロードする行動へとつながります。
ダウンロードの際にフォームを設置することで、見込み顧客の情報を取得することが可能となり、その後の営業・マーケティング施策にも活用できます。特にBtoB分野では、購買検討段階の顧客がホワイトペーパーを読むことが多く、より質の高いリードの獲得につながるというメリットがあります。
営業活動の効率化とブランド認知度の向上
営業活動においても、ホワイトペーパーは非常に有効です。見込み顧客に対して単なるセールスではなく、「役立つ情報提供」を通じて接点を築けるため、信頼感を醸成しやすくなります。
また、ホワイトペーパーを活用することで、営業担当者の説明時間や資料作成の工数を削減できるなど、業務の効率化にもつながります。さらに、専門的で整ったコンテンツを発信することで、企業のブランディング強化や信頼性向上にも貢献します。
Web広告やSNS投稿と連動させることで、ホワイトペーパー自体がブランド認知の接点となり、潜在層へのアプローチも可能になります。
製品・サービスに対する信頼度アップ
顧客が製品やサービスを選ぶ際、「本当に信頼できるのか?」「他とどう違うのか?」という疑問を持つのは自然なことです。ホワイトペーパーは、そうした不安や疑念に対して論理的かつ具体的に答える手段となります。
例えば、導入事例や市場データ、ユーザーインタビューを盛り込んだホワイトペーパーは、客観的な証拠として信頼度を高める要素になります。特に、比較検討段階にいる見込み顧客に対しては、購入や導入の後押しをする強力な材料となるでしょう。
また、自社の専門性や取り組み姿勢を可視化することで、単なる製品紹介では伝えきれない価値を届けることができます。信頼性のある情報を蓄積し、ユーザーとの関係構築に活かす点においても、ホワイトペーパーは非常に重要な役割を担っています。
事前に確認しておきたいポイント

ホワイトペーパーを効果的に制作・活用するためには、着手前の段階でいくつかの重要なポイントを事前に整理しておくことが欠かせません。この準備が不十分だと、的外れな内容になってしまったり、成果につながらない事態に陥る可能性があります。
ここでは、制作前に必ず確認しておきたい3つの要素について詳しく解説します。
目的とターゲットの明確化
まず最初に行うべきは、「ホワイトペーパーで何を達成したいのか?」という目的の明確化です。リード獲得を狙うのか、顧客の理解を深めたいのか、商談の後押しとして使いたいのかで、構成や内容は大きく変わります。
同時に、誰に読んでもらいたいのかというターゲット設定も重要です。役職、業種、課題、購買フェーズなどを具体的に想定し、ペルソナを設定することで、読み手に響く内容がブレなくなります。
たとえば、情報収集中の段階にいる見込み顧客には、基礎的なノウハウや課題整理の資料が効果的ですが、比較検討フェーズの読者には、事例紹介や機能比較などがより有効です。目的とターゲットが一致して初めて、成果につながるホワイトペーパーが完成します。
競合調査と差別化戦略
続いて重要なのが、競合企業がどのようなホワイトペーパーを提供しているかの調査です。市場にすでに存在する資料を分析することで、内容の重複や見劣りを防ぎ、自社ならではの切り口を見つけるヒントになります。
例えば、よくある「導入事例集」や「課題解決マニュアル」に対して、より専門的なデータや独自の調査結果を組み込むことで、差別化されたコンテンツが制作可能になります。
差別化の鍵は、「自社だからこそ伝えられる情報とは何か?」を見極めること。顧客の視点に立ち、他社資料では得られない価値を提供することが、読者の心を動かす最大のポイントになります。
スケジュールとリソース管理
ホワイトペーパー制作には、企画・ライティング・デザイン・確認・公開といった複数の工程が存在し、想像以上に時間と人手がかかるものです。特に社内での複数部署との調整や、確認・修正にかかる時間を見落とすと、リリース時期がずれ込んでしまうことも少なくありません。
そのため、事前に制作スケジュールを逆算し、各工程にどの程度の時間とリソースを割くかを計画しておくことが不可欠です。
また、ライティングやデザインなどを外注する場合は、依頼先との連携方法や納期管理、修正回数の確認なども事前に取り決めておくべきです。
限られた予算・人材で最大限の成果を出すには、社内外を問わず「誰が・いつまでに・何を担当するのか」を明確化し、計画的に進行することが成功の鍵となります。
ホワイトペーパーの種類と構成例
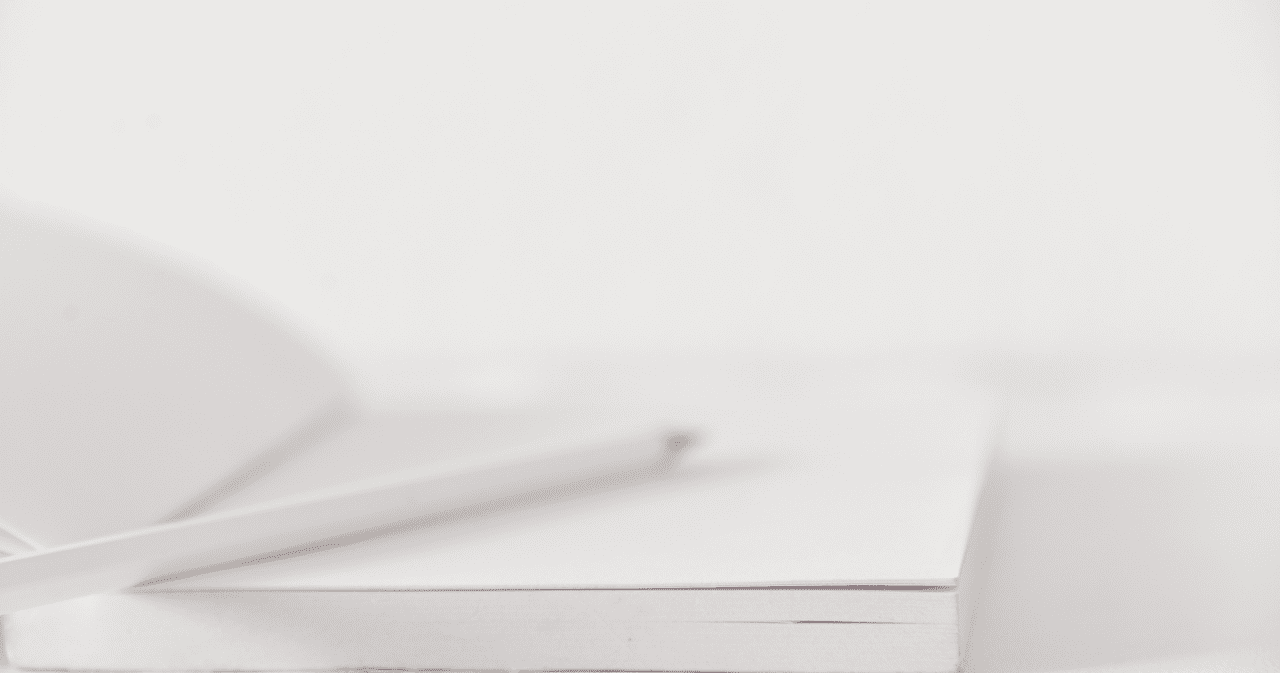
ホワイトペーパーは、目的やターゲットによってさまざまな形式が存在します。それぞれに特化した構成や内容があり、用途に応じたタイプを選ぶことが成果を高めるカギとなります。
ここでは、代表的な4種類のホワイトペーパーとその構成例を紹介します。
課題解決型:対策一覧やHowTo資料
課題解決型ホワイトペーパーは、読者が抱える悩みや課題に対して、具体的な解決策や方法を示すことを目的とした資料です。
たとえば、
- 業務効率化のステップ
- マーケティング施策のチェックリスト
- セキュリティ対策の導入手順
といった内容がよく見られます。
構成例:
- 読者の課題背景とその重要性の提示
- よくある失敗パターンとその原因
- 解決のための具体的な施策や手順
- 導入による効果と実行のコツ
このタイプは、「今すぐ役立つ情報」を求める見込み顧客に刺さりやすく、ダウンロード率も高い傾向があります。
ケーススタディ型:具体的成功事例
ケーススタディ型ホワイトペーパーは、実際の導入事例や顧客の成功体験を紹介しながら、自社サービスの効果や有用性を伝えるスタイルです。
読者にとっては、他社の取り組みを参考にできるという安心感があり、「自社でも実現できるのでは?」という期待感を与えることができます。
構成例:
- 企業プロフィール(業種・規模・背景)
- 抱えていた課題と導入の経緯
- 導入プロセスと対応内容
- 導入後の効果と定量的成果
- 担当者インタビューやコメント
とくにBtoB領域では、同業界・同規模企業の事例が読者に強く刺さるため、ターゲットに合わせた事例選定が重要です。
データレポート型:統計情報や市場動向
データレポート型ホワイトペーパーは、業界動向やユーザー調査、アンケート結果などをもとにした分析レポート形式の資料です。
信頼性の高い情報源として多くの読者に支持され、ブランディングや権威性の構築にもつながるのがこの形式の強みです。
構成例:
- 調査概要・対象・目的
- 主な統計データやグラフの掲載
- 結果の分析・考察
- 読者にとっての示唆・次のアクション
マーケティングオートメーション(MA)やリードナーチャリング施策との連携においても、精度の高いターゲティングが可能になるため、継続的な活用にも向いています。
プロダクト・サービス紹介型:比較検討資料
プロダクト・サービス紹介型ホワイトペーパーは、見込み顧客が自社製品やサービスを導入するメリットを具体的に理解できるように構成された資料です。競合製品との違いを明確に打ち出すことで、比較検討段階の読者にアプローチします。
構成例:
- 製品・サービスの概要
- 想定課題とその解決方法
- 他社製品との比較ポイント
- 導入メリットと利用事例
- よくある質問と導入サポート
このタイプは、問い合わせや商談への移行率を高める目的で用いられることが多く、営業資料としても汎用性が高いのが特徴です。
このように、ホワイトペーパーは種類ごとに役割やターゲットが異なります。目的や顧客のフェーズに応じて最適なフォーマットを選定し、自社の強みが活きる構成を意識することが成功の鍵となります。
ホワイトペーパー制作の流れ

ホワイトペーパーは、「作って終わり」の資料ではなく、マーケティング施策として成果を生み出すプロセス全体が重要です。そのためには、各ステップを明確に把握し、計画的に進めることが欠かせません。
ここでは、制作の基本的な流れと各ステップの要点について解説します。
テーマ設定とアウトライン策定
最初に行うべきは、ホワイトペーパーのテーマ設定と構成の設計です。
「誰に」「何を伝え」「どういう行動を促したいのか」を明確にし、読み手の課題や関心にフィットしたテーマを選ぶことが成功の第一歩です。
テーマが決まったら、以下のような項目を軸にアウトライン(構成案)を組み立てます。
- 導入(課題の提示)
- 本文(解決策や事例の紹介)
- 結論・CTA(次の行動を促す)
無理に詰め込まず、1テーマ1メッセージを意識した構成が、読みやすく成果につながりやすいホワイトペーパーになります。
原稿作成とライティングのポイント
アウトラインが固まったら、次は**原稿の作成(ライティング)**に移ります。
ポイントは以下の通りです:
- ターゲットの理解度に応じて専門用語を使い分ける
- 結論ファーストで伝える(読み手の離脱を防ぐ)
- 根拠となるデータや事例を盛り込む
- 読みやすさを意識して、見出し・箇条書き・図表を活用
また、ホワイトペーパーは信頼感が重要なため、過剰な売り込み表現は避け、あくまで“中立的な立場での情報提供”が基本姿勢です。
インタビューや社内資料を元に原稿をまとめる場合は、文章構成の一貫性や客観性を保ちながら、伝えるべき要素を整理する編集スキルも求められます。
デザインとレイアウト
ライティングが完了したら、次はデザイン・レイアウトのフェーズです。ここでは、単に「見栄えが良い」だけでなく、情報が伝わる・読みやすい・行動を促すことがデザインの目的となります。
主なポイントは以下の通り:
- ブランドイメージに合ったカラーやフォント選定
- 見出し・図表・アイコンで視認性を高める
- CTAボタンやリンクの配置で導線を設計
- モバイルやPDF印刷にも対応できる構成
特にBtoB分野では、信頼感や専門性を伝える洗練されたデザインがリード獲得に直結するため、デザイナーとの連携も非常に重要です。
公開後の効果測定と改善
ホワイトペーパーは、公開して終わりではなく、そこからがスタートです。公開後は必ず効果測定と改善サイクルを回しましょう。
主なチェック項目には以下があります:
| 指標 | チェック内容 |
| ダウンロード数 | ページ閲覧数との比較でCV率を確認 |
| 読了率 | 内容の分かりやすさや長さの適正を判断 |
| 獲得リードの質 | 商談化率・継続的接触の有無など |
| 拡散状況 | SNSシェア数、Web媒体への掲載状況など |
データに基づいて「タイトルの改善」「CTAの見直し」「フォームの項目削減」などを実施することで、ホワイトペーパーの成果を継続的に高めていくことが可能です。
このように、ホワイトペーパー制作には設計・執筆・デザイン・活用・改善という一連の流れがあり、それぞれが成果に大きな影響を与えます。
一つひとつの工程を丁寧に進めることが、信頼され、ダウンロードされるホワイトペーパー制作への近道です。
ホワイトペーパー制作代行会社の選び方

ホワイトペーパーの品質は、そのまま企業の信頼性や成果に直結します。社内での制作が難しい場合、制作代行会社への依頼は非常に有効な選択肢です。しかし、代行会社によって得意分野や対応範囲、価格、体制が大きく異なるため、慎重に選定することが重要です。
ここでは、ホワイトペーパー制作代行会社を選ぶ際に確認すべき4つのポイントを紹介します。
実績と専門領域の確認
まず重視すべきは、その会社が過去にどのようなホワイトペーパーを制作してきたかという実績です。特に、
- 同業種や類似サービスの制作経験
- BtoBマーケティングに精通しているか
- 成果につながった事例(リード獲得数など)があるか
といった点は、信頼性の判断材料になります。
また、業界によって求められる専門知識が異なるため、自社と近い分野での専門性があるかを確認することも重要です。必要であれば、ポートフォリオやサンプル資料を請求して中身をチェックすることをおすすめします。
費用の相場と見積もり比較
制作代行会社を選ぶ際には、費用感が適正かどうかも重要な判断ポイントです。一般的にホワイトペーパー制作の費用は以下のような内訳で構成されます。
| 費用項目 | 相場目安 |
| 企画・構成案作成 | 5万〜15万円 |
| ライティング(原稿作成) | 10万〜30万円 |
| デザイン・レイアウト | 10万〜25万円 |
| 合計 | 25万〜60万円程度 |
価格だけで判断するのではなく、提供されるサービス内容と見積もりの内訳を丁寧に比較検討することが大切です。また、修正対応の範囲やオプション(翻訳や印刷対応など)も確認しておくと、後々のトラブルを防げます。
納期とコミュニケーション体制
ホワイトペーパーは制作期間が長期にわたることも多いため、円滑なコミュニケーション体制は必須です。具体的には以下のような点を事前に確認しましょう。
- 担当者は専任か複数名体制か
- 打ち合わせは定期的に行われるか
- 修正依頼に柔軟に対応できるか
- 進行管理の体制が整っているか
また、納期に対する意識や余裕のあるスケジューリングができるかどうかも大きなチェックポイントです。タイトな納期でも対応可能な場合は、そのぶん費用が上がるケースもあるため注意が必要です。
対応範囲:企画から配信まで
最後に、制作代行会社がどこまで対応してくれるかという「対応範囲」も非常に重要です。例えば、
- ターゲットやペルソナの策定
- 競合調査やコンテンツ企画
- 原稿ライティング
- デザイン制作
- ダウンロードページの設計
- 公開後の分析や改善提案
など、ワンストップで対応可能な会社であれば、社内工数を大幅に削減でき、品質の一貫性も保ちやすくなります。
部分的に内製し、必要な部分だけ外注するハイブリッド型も選択肢の一つです。自社の体制と照らし合わせながら、どこまで任せたいのかを明確にし、それに応じた制作会社を選びましょう。
制作代行会社選びは、成果に直結するパートナー選びです。焦らず、丁寧に比較検討することが、信頼できる会社との出会いにつながります。
ホワイトペーパー制作の費用相場と予算の考え方

ホワイトペーパー制作は、マーケティング投資として非常に効果的ですが、ある程度の予算を要する施策でもあります。とはいえ、項目ごとの内訳やコストのかけ方を把握すれば、無駄なく費用対効果の高い運用が可能です。
ここでは、ホワイトペーパー制作にかかる代表的な費用項目と、予算設計のコツを解説します。
料金内訳:企画・ライティング・デザイン
ホワイトペーパーの費用は、主に以下の3要素で構成されます。
| 項目 | 内容 | 相場目安(税抜) |
| 企画・構成案の策定 | ターゲット・目的の整理、アウトライン作成など | 5万~15万円 |
| ライティング(原稿作成) | リサーチ・インタビュー・文章作成 | 10万~30万円 |
| デザイン・レイアウト | 表紙・本文レイアウト、図表作成など | 10万~25万円 |
全体で約25万~60万円が一般的な相場となっており、ページ数やコンテンツの難易度によって変動します。特に専門性の高い業界や、インタビューを含む場合は、ライティング費用がやや高くなる傾向があります。
追加オプション(翻訳・印刷など)の有無
基本の制作費用に加えて、目的や活用方法に応じて追加費用が発生するケースもあります。
主なオプションには以下のようなものがあります。
| オプション内容 | 相場目安 | 補足 |
| 英語・多言語翻訳 | 5万~15万円/言語 | 海外展開を視野に入れる企業向け |
| 紙媒体での印刷・製本 | 数千円~ | セミナー配布など対面活用時に有効 |
| データ分析・改善提案 | 5万~10万円程度 | 公開後の効果測定まで任せる場合 |
こうしたオプションの有無によって、総予算は大きく変わるため、最初に活用目的を明確にし、必要な機能だけを選定することが重要です。
コスト削減のポイント:社内リソース活用
限られた予算の中でホワイトペーパーを効果的に制作するには、社内で担える部分と外注すべき部分を見極めることが重要です。
たとえば以下のような対応が考えられます。
- 企画や構成案は社内で策定し、ライティング・デザインのみ外注する
- 社内のマーケティング部や営業部から原稿の叩き台を集め、ライターはリライト中心に対応
- テンプレートを活用してデザイン費を圧縮する
また、1本のホワイトペーパーを複数のチャネル(SNS・広告・セミナーなど)で展開することで投資効果を最大化するという発想も、費用対効果を高めるうえで有効です。
ホワイトペーパーは一度制作すれば、繰り返し使える「資産型コンテンツ」です。無理のない範囲で効果的に活用するためにも、全体予算と費用配分をあらかじめ設計し、長期的な視点で計画を立てることが重要です。
ホワイトペーパーの効果的な活用事例

ホワイトペーパーは、制作して終わりではなく、どのように活用するかが成果を左右する重要なポイントです。実際のビジネス現場では、マーケティング施策の中で多様な形で展開され、リード獲得や商談創出に直結する成果を生み出しています。
ここでは、特に効果が高い3つの活用シーンを紹介します。
マーケティングオートメーション(MA)との連携
MA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携は、ホワイトペーパーを最大限に活かす手法の一つです。ダウンロードをトリガーに、ユーザーの行動に応じてメールを自動配信したり、スコアリングによって商談フェーズに応じた情報提供が可能になります。
たとえば以下のような連携が一般的です:
- ホワイトペーパーのダウンロード→フォローアップメールの自動送信
- 複数回資料を閲覧したユーザー→営業チームに通知・アプローチ
- 関連するテーマの資料→シナリオ型でナーチャリング
MAとの連携により、見込み顧客との関係性を中長期的に育てる「ナーチャリング施策」として活用できるのが大きなメリットです。
WEB広告やSNSによる拡散
せっかく作成したホワイトペーパーも、読んでもらわなければ意味がありません。そこで有効なのが、Web広告やSNSを通じた拡散施策です。
特に、
- リスティング広告やディスプレイ広告での訴求
- FacebookやLinkedInなどSNSでのシェア
- オウンドメディアや記事との連動導線
など、多面的な導線設計によってダウンロード数を飛躍的に伸ばすことが可能になります。
また、広告のABテストを行いながら、訴求軸やターゲティングを最適化することで、より高精度なリード獲得につなげることができます。
イベントやセミナーでの活用
リアル・オンラインを問わず、イベントやセミナーでの資料配布用としてホワイトペーパーを活用するケースも非常に効果的です。
たとえば、
- 展示会ブースでの配布資料
- ウェビナー終了後のフォローアップ資料
- 相談ブースでの理解促進用コンテンツ
など、営業担当者が手元に置いて活用できる「補助資料」としても優秀です。
特にセミナー参加者は課題感や情報収集意欲が高いため、ホワイトペーパーの内容次第で商談への移行率が大きく変わることも少なくありません。
このように、ホワイトペーパーはデジタル施策とリアル施策の両方で柔軟に活用できる汎用性の高いマーケティングツールです。制作後の展開方法を事前に計画しておくことで、費用対効果を最大化し、継続的なリード獲得につなげることが可能になります。
よくある質問(FAQ)

ホワイトペーパーの制作を検討する際、多くの担当者が抱える疑問についてお答えします。実際の制作現場でよく寄せられる質問を取り上げ、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。
ホワイトペーパー制作にかかる期間はどのくらい?
ホワイトペーパーの制作期間は、内容の複雑さや社内外の確認体制によって異なりますが、一般的には1ヶ月〜2ヶ月程度が目安です。
以下はおおよその工程と目安期間です:
| 工程 | 所要期間の目安 |
| テーマ・構成の企画 | 1〜2週間 |
| 原稿作成(リサーチ・ライティング) | 2〜3週間 |
| デザイン・レイアウト | 1〜2週間 |
| 修正・確認・納品 | 1週間前後 |
社内での確認や調整に時間がかかる場合は、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。制作会社に依頼する場合も、事前に納期や進行方法を確認しておきましょう。
ページ数はどれくらいが適切?
ホワイトペーパーのページ数は、目的やターゲットに応じて変動しますが、一般的には6〜12ページ程度が読みやすく、適切なボリュームとされています。
- 6〜8ページ前後:シンプルな課題解決型やサービス紹介型に最適
- 10〜12ページ以上:データレポート型やケーススタディ型など、情報量が多い資料に向いています
重要なのは「長さ」よりも情報の濃度と構成の分かりやすさです。過剰にページを増やすより、ターゲットにとって本当に必要な情報に絞ることが、ダウンロード後の読み進め率や理解度の向上につながります。
成果につなげるためのテクニックとは?
ホワイトペーパーをただ作るだけで終わらせず、成果につなげるためには以下のようなテクニックが有効です。
- ペルソナに基づいた内容設計:誰に向けて書くのかを明確にすることで、刺さるメッセージが届けられる
- CTA(行動喚起)の設置:資料の最後に「お問い合わせはこちら」「関連資料はこちら」などの導線を設ける
- SEOを意識したLP設計:ダウンロードページ自体も検索流入を意識して構成し、オウンドメディアとの連携を図る
- MAツールや広告との連携:ホワイトペーパーを起点にリードナーチャリングを自動化し、成果までの導線を作る
- 定期的な改善と更新:古くなった情報や成果が出ない箇所は随時見直すことで、鮮度と効果を保てる
これらを実行することで、ホワイトペーパーが単なる資料ではなく、営業・マーケティングを後押しする強力な武器となります。
総括:今すぐ取り組むべきホワイトペーパー制作のポイント

ホワイトペーパーは、BtoBマーケティングにおけるリード獲得・顧客育成・営業支援に非常に効果的なコンテンツです。ただし、成果を出すためには「何を伝えるか」「誰に届けるか」「どう活用するか」といった視点を持ち、計画的かつ戦略的に制作を進める必要があります。
本記事で解説してきたポイントを改めて整理すると、以下のようになります。
- 目的とターゲットを明確にした上で、種類や構成を選ぶこと
- 課題解決型・ケーススタディ型など、内容に応じたホワイトペーパー形式を活用すること
- マーケティングオートメーションや広告、セミナーと連携させ、継続的に運用すること
- 社内リソースと外注のバランスを取りつつ、スケジュールと予算を最適化すること
- 制作後も効果測定と改善を繰り返し、より高い成果へとつなげること
ホワイトペーパーは一度作って終わりの資料ではなく、企業のマーケティング活動を支える「資産」となります。競合が情報発信を強める中で、今こそ他社に差をつけるチャンスです。
もし「自社での制作が難しい」「どこから始めればよいかわからない」とお悩みであれば、専門の制作代行会社に相談するのも有効な手段です。豊富なノウハウを活かして、目的に合ったコンテンツを効率的に形にすることができます。
まずは1本、見込み顧客に届くホワイトペーパーを作ってみるところから始めてみましょう。
その一歩が、未来の商談や成果につながる大きな第一歩になります。